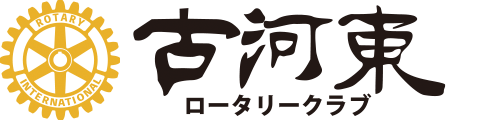杉岡榮治SAAより
▶ 2024/10/21 ハーバート・テーラー「四つのテスト」
言行はこれに照らしてから;
1 真実かどうか
2 みんなに公平か
3 好意と友情を深めるか
4 みんなのためになるかどうか
「四つのテスト」は1933年にシカゴロータリークラブのハーバート J.テーラー(1893年ミシガン州生まれ)が提唱したものです。
1939-40年度のシカゴロータリークラブ会長を46歳で務め、ロータリー創立50周年である1954-55年度のRI会長に61歳で就任しています。このロータリー創立50周年に際して、「四つのテスト」の版権を国際ロータリーに寄贈しています。
商才に恵まれ、ジュエル・テイー社の次期社長候補だった1932年(39歳)、倒産寸前のクラブ・アルミニュウム社の再建を依頼され、従業員数250名を抱え、40万ドルを上回る負債のある倒産寸前の医療器具メーカーの社長に就任しました。
彼は、再建にあたり、倫理的、道徳的な経営を行えば必ず再建できるだろうと考えました。そこで、従業員が、正しい考え方を持ち正しい言動を行えるような指標が必要だということで、最初にできたものは、7項目の標語でしたが、もっと簡単なものが良いと考え、4つの項目に絞り、現在の「四つのテスト」になりました。
全従業員がこのテストに沿って考えたり、言ったり、行動したりするうちに、社会的な信用が高まり、5年後には借金を完済し、15年後には株主に多額の配当を出せる優良企業になりました。
例えば、出入りの印刷業者が500ドル安い見積りを出してしまい、納品後にそのミスに気づきました。その事情を聞いた担当者は、気持ちよく、500ドルを上乗せして支払ったそうです。
また、以前の広告では、「世界最高の・・・」「最も良い・・・」という表現を使用していたものを、本当に世界一なのか証明するものはないし、そうでないかもしれないという理由で取りやめ、製品についての事実だけを述べることにしました。
このほか、ある安売り業者(デイスカウント業者)から大量の注文があり、幹部もろとも大喜びしたのですが、極端な安売りをされると地道に商売している他の小売店に迷惑がかかり、結果として不公平が生じるのではないか、この取引がみんなのためになるかどうかが問題となり、結局、その取引は行わないことにしました。
「四つのテスト」が徐々に従業員の間に浸透するに従い、新しい、潤いのある社風となり、取引先、顧客、従業員の同社に対する信頼と好意が生まれ、倒産寸前の会社が優良企業に生まれ変わったのです。
基本的に、これはクラブ・アルミニュウム社の再建のために考えられたものですが、
友好的な人間関係を構築するものなので、職業生活だけでなく、個人生活、社会生活の
すべてに活用できる判断基準だと思います。
「四つのテスト」の和訳は、1954年に日本中のロータリアンから一般公募を行い、70数件の応募の中から、東京ロータリークラブの本田親男氏のものが採用されて今に至っています。
この指針を忠実に実行する困難さは、4項目が別々にあるのではなく、4項目ともクリアーすることを要求されていることです。今日は3項目クリアしたので75点、というわけにはいかないようです。
完璧な実践は非常にハードルが高い気がしますが、行動指針として、クリアーできるよう努力をすることに大きな意味があると思います。 (SAA 杉岡榮治)
The Four-way Test of the things we think, say or do:
1. Is it the TRUTH?
2. Is it FAIR to all concerned?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned?
▶ 2024/10/21 超我の奉仕・奉仕の理念
超我の奉仕 Service above self とは、事務総長として永年ロータリーに貢献したチェスレー・ペリー(Chesley R. Rerry)の解釈によると、「利己の心を超越して他人のことを思いやり他人のために尽くすこと」と言われています。
『ロータリーの目的』に3回出てくる奉仕の理念 Ideal of serviceとは、具体的には、①他人への思いやり、②助け合いの心、③他人の身になる心 ということのようです。 (SAA 杉岡榮治)
お気軽にお問い合わせください。Mail Form Only受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ