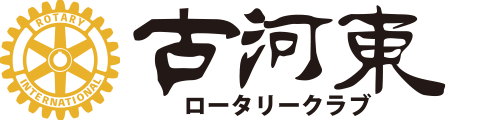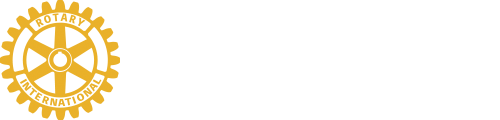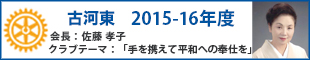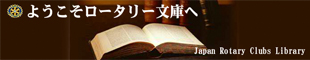会長の時間(40)

「税務調査はいつ来るの?」
昨年11/26の「会長の時間№20」で「ロータリー年度」の由来の際に、ロータリーの年度は、国際大会が当初8月に開催されており、後に6月末を会計年度末とするのが良いとの事から、7/1に始まり6/30までとする年度になった経緯をお話しました。その際に、皆さんの事業所の事業年度はいつでしょうか?や、官公庁関係、学校、各種税務関連団体等の会計年度は?などお聞きしながら、例外として、税務署等の国税に関連する組織は、7/1から6/30が1事務年度となり、これに合わせて税務署の定期人事異動もその年度7/10となる旨の話(理由は、3/15の確定申告期と2割を占める3月決算法人の5/末提出を考慮)でした。お待ちしている方はいないと思いますが(私の顧問先で何件かの社長さんが、間違いがあれば正せるし、ネジを巻いてもらいに時々は来ていただいた方がいいんだよと言っていました!)、通常「税務調査というのは、いつ来るのでしょうか?」
税務調査は、大きく2つに分かれて1任意調査と2強制調査となります。皆さんが通常、調査を受けられているのが1任意調査で、2強制調査は、端的に言って国税通則法に基づき国税局査察部によって実施される調査で、あまりなじみがないので、今回は2強制調査には触れず、1任意調査のみとします。
税務署にも、この1事務年度には、皆さんの事業所と同じく「繁忙時期」があり、「実施しやすい時期」と「あまり実施されない時期」があります。そして税務署の署員には、年度初めに、各担当課税の税務調査の「件数」や「金額」などの目標(ノルマ)が示されるはずです。当該達成のスタートダッシュを図るために最も活発に調査が行われるのは、年度の始まり(7月。実際には移動事務等もあるので8.9月)から年末(12月)までの約半年(上期)です。年が明けて、下期に入り1月、2月にも税務調査は行われますが、確定申告の期間(2/16-3/15)が近づき、税務署の方も多忙が予想され、ある程度調査を早めに取りまとめる段階に入ります(現実はそうならない場合もあります)。またこの時期から取り掛かるには、税理士の方も良い顔はしないので、先送りになる可能性(あるいは短期間で終了する可能性)があります(絶対的ではありません)。この意味で税務調査は上期の方が実施される件数が多くなります。またこの確定申告期間中は、税理士会側としてもが調査に入らないように申入れをしています。確定申告期間が終わると3/16以降、最終コーナーに入り約3ヶ月間の最後のノルマ達成に入ります。但し5月に入ると、前述の通り、法人企業提出の2割を占める3月決算法人の5/末提出を考慮しなければならなくなります。しかしこれはあくまで税理士が多忙になるだけで税務行政側は無関係であるので、是が非でも実施したい旨が見え隠れする時期となります。6月になれば、着任後1年内の署員以外は、残りの税務調査の整理、残務整理、引継ぎ準備などがあるので、新規開始はあまりありません。この辺りから逆算して法人事業所の事業年度を決めている方がいるとかいないとか聞いたことがありますが、いずれにしましても、証憑書類を基に、各税法や企業会計原則に従い適正に会計処理され、期限内に申告、納付されていれば問題となるところはないはずです。何もやましい事が無いのですが、どうしても来るとなると緊張しすぎて、何十年ぶりの面接を受けている感じなのか普段と違い、言動や行動がおかしくなる方も時々いらっしゃいます。
最後に、税理士の立場をより尊重し、納税者の適正申告の向上や更なる納税者との信頼関係築くものとして、申告納税制度のもと税理士の権利の一つとして、書面添付制度(税理士法第33条の2。この他に同法第35条に規定する意見聴取制度)があります。平成13年の税理士法改正において事前通知前の意見聴取制度が創設され、その存在意義を飛躍的に拡充したうえで、新たにスタートしました。 税理士だけに認められた権利で、その活用により実地調査の省略や効率化が図られることになり、納税者の負担軽減になるとともに、納税者に対して税理士の存在意義をより明確に表し、ひいては税務行政負担の円滑化、簡素化の一役を担います。 したがって、この制度の活用は、税理士の社会的評価の向上に大きな意味を持ち、信頼される税理士制度確立のための大きな手段となります。
ロータリーにおいても、2017年に「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。」とビジョン声明を発表しました。これにより入会者、協力団体、寄付者にとって魅力あるクラブであり続けることが出来ます。我々もロータリーにかかわり、日々、奉仕の理念を実践し、永遠の奉仕を目指して、クラブを活性化し、そして「仲間を増やして、強いクラブを作って参りましょう」。